クリムト、シーレ 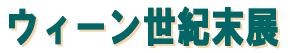 |
 |
||
|
|||
|
|
| 第1章 装飾美術と風景画 | |||
|
第1章は、19世紀末から20世紀の初めまでの、数多くの画家たちの作品が並んでいました。聞いたことがない画家の作品ばかりなので、作品番号と解説をチェックしてメモを取りながらじっくり見て回わりました。 |
 |
||
| 「山ツツジ」 マリー・エグリー (1896年) | |||
 「イーゼルの前の 自画像」
|
|||
| 第2章 グスタフ・クリムト | ||||

「テレーゼとフランツ・マッチュ」 |
続いては、この展覧会の主役の1人グスタフ・クリムトのコーナー。クリムト自身の作品は8点展示されていましたが、彼と関連の深かった2人の画家の作品もこのコーナーにありました。まずは、簡単な経歴をご紹介したいと思います。 |
|||
 |
||||
 「寓話」 グスタフ・クリムト 「寓話」 グスタフ・クリムト(1883年) ツルはキツネにもらった平たいお皿に入った食べ物をうまく食べれないが、逆にキツネはツルの細口の瓶に入った食べ物を食べることができない(→) また、ネズミを助けたライオンは、今度は自分が罠にはまって動けなくなった時に、ネズミに助けられた。 |
||||
 |
||||
| 「牧歌」 グスタフ・クリムト (1884年) |
||||
|
続いて、2点出品されていた弟のエルンスト・クリムトの作品の1つを紹介したいと思います。 |
|||

「宝石商」 エルンスト・クリムト (1889年) |
|||
 |
|||
|
「パラス・アテナ」 グスタフ・クリムト |
|||

|
|||
| 第3章 エゴン・シーレ | |||
「意地悪女」 |
さて、次はこの展覧会のもう一人の主役エゴン・シーレのコーナーです。最初の方に、ウィーン美術アカデミーの仲間で、後にシーレの妹のゲルとルーデと結婚したというアントン・ペシュカの描いたシーレの肖像画がありました。これは個性的な色彩でした。その色遣いをうまく説明できませんが、レインボー系のようなかんじでした。 |
||
 「自画像」 1911年 |
|||
 「アルトゥール・レスラー」 1910年 |
|||
 「家族」 1918年 |
|||
| 第4章 分離派とウィーン工房 | |||
|
クリムトらが設立した「ウィーン分離派」は、自分たちの作品の展覧会ではなく、印象派や日本美術などを紹介する展覧会を積極的に企画し、ウィーン世紀末芸術の展開に大きな影響を及ぼしました。 |

「ウィーン工房のハガキ」 |
||
|
供しようというコンセプトのもと、建築、工芸、家具、食器、服飾、書籍など生活に密着したあらゆるジャンルに製品が生み出されました。それらの製品は、ウィーンだけでなくベルリンやチューリッヒ、ニューヨークに支店でも販売されていたそうです。 |
|||
|
本日はここまで! |
|||